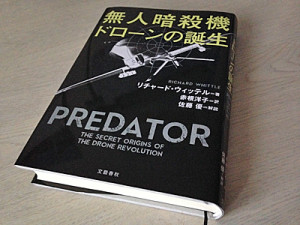2015年03月 の投稿一覧
『吉原まんだら 色街の女帝が駆け抜けた戦後』清泉亮
Posted by 大熊 一精 on 2015年3月22日(日) 19:49
『吉原まんだら 色街の女帝が駆け抜けた戦後』清泉亮(徳間書店,2015年3月刊)
大正10年生まれ、今年で94歳になる「おきち」こと高麗きちの半生を軸に、東京・吉原の近代を描いた重厚なノンフィクションです。
昭和26年12月26日、深川で夫が営む金物屋を手伝っていた「おきち」は、夫の「おいっ、吉原買ったぞ。吉原行くぞ」の一言で、深川から吉原へと居を移します。それは、おきちの夫が博打の形にもらったという一軒家でした。
《吉郎は、「おいっ、ここで商売をやるぞ」と言いだした。「ここで商売」と言われれば、決まっていた。その場所で、ほかにどんな商売があるというのだろうか。まだ30歳そこそこのおきちにとってはしかし、何をどうやっていいのかさっぱり分からない。》(第1章 来たれもん、吉原に立つ)
以来60年余、おきちは、現在に至るまで、その家で暮らしながら、吉原で「赤線」「トルコ」「ソープ」を営んできました…と書くと、それだけで眉を顰める向きもありましょうが、そのような商売が連綿として続けられてきたことには、「必要悪」などといった言葉では語りきれないほどの理由があることが、本書を読み進めていくと、よくわかります。理由がどうこうではなく、さまざまな要素が絡み合った結果の必然であるとすら思えます。
本書の中心になっているのは、90歳を超えたおきちからの聞き書きですが、それだけではありません。著者は、めったに姿を見せないおきちの元に通いながら、おきちからさらにおもしろい話を引き出すために、あるいはおきちが手元に残している古い文書を元に、おきちも知らない、しかしおきちが喜ぶ吉原の歴史を、粘り強い取材で掘り起こしていきます。
とりわけ、「角海老」の創業者=明治26年に谷中で執り行なわれた葬儀は岩崎弥太郎の葬儀以来の規模だったと樋口一葉が書き残している人物=の実像を探し当てていく過程は、拍手を贈りたくなるほどの大仕事です。
きわめて個人的な話になりますが、私は「小江戸」と呼ばれた町で26歳までを過ごしました。自分の父親や、父方の親戚の喋りには、下町言葉が混じっていました。「この商売はよ、人殺しを使えるようじゃなきゃやってらんねーんだよ」と語るおきちの言葉は、現代の標準的な日本語からすれば、とても女性が発したものとは思えない言葉ですが、私が26歳まで過ごした町には、おきちのような喋りをする年配女性が、実際に、たくさんいました。そんなこともあって、本書の中に多数登場する、カギカッコで括られたおきちの言葉には、文字なのに音で聞こえてくるようなリアリティがあります。
著者のおきちに対する優しい視線が、心地よい読後感を生んでいる本です。
『無人暗殺機ドローンの誕生』リチャード・ヴィッテル(訳=赤根洋子)
Posted by 大熊 一精 on 2015年3月1日(日) 09:10
『無人暗殺機ドローンの誕生』リチャード・ヴィッテル(訳=赤根洋子)(文藝春秋,2015年2月刊)
アメリカにおける無人航空機の開発過程を、スリリングに描いたノンフィクションです。
本書は、1973年、中東戦争の続くイスラエルで、航空機の設計を担当していたエイブ・カレムが、空軍から無人航空機の開発を依頼される場面から始まります。その目的は、空中から目標を攻撃する戦闘機を狙って飛んでくる地対空ミサイルに対し、無人機を囮として飛ばすことで地対空ミサイルの目標を誤認させることでした。レーダーが囮の無人機を戦闘機だと誤認すれば、ミサイルが撃ち落とすのは無人機になり、有人の戦闘機はミサイルの標的となることなく敵の目標を攻撃することができます。
すぐれた航空技師であった当時36歳のカレムは、この依頼に応じて基本設計を空軍に提供した後、ひらめきを得て新たな無人機の開発に乗り出しますが、自分の開発環境が実質的にイスラエル政府の支配下に置かれていることに嫌気がさして、アメリカへと渡っていきます。
一方、アメリカでは、ニールとリンデンのブルー兄弟が、武装無人機の開発に取り組んでいました。彼らが着目したのは、1983年の大韓航空機撃墜事件を契機に実用化されつつあったGPSでした。GPSを使って無人機をピンポイントで目的地へと誘導し敵への攻撃を行えば、無差別爆撃によって非軍人を巻き添えにすることは避けられる−そう考えた彼らは、また、根っからの起業家であり、資金を調達して技術開発の母体となる企業を買収し、そこへ退役した戦闘機乗りのトマス・キャシディを招きます。彼らはGPS誘導無人機の試作機を「プレデター」と名付けます。
1988年、アメリカ航空宇宙博で、カレムとブルー兄弟が出会うことから、プレデターは、実用化に向けて急速に動き始めます。ブルー兄弟はカレムが培ってきたあらゆる技術を(本書の言葉を使えば「冷血な資本主義者」の顔で)買収します。そして、1992年に旧ユーゴスラビアで始まった民族紛争で、プレデターは無人偵察機として実戦に投入されます。プレデターには、それまでの無人機とは桁違いの航続時間の長さという長所がありました。
実戦で評価を高めたプレデターには、新たなミッションが与えられます。偵察機が目標を発見してから別の戦闘機が現場へ向かって攻撃を仕掛けるまでのタイムラグという戦術的な問題を解決するために、プレデター自身に攻撃能力を持たせることが、次の開発目標となるのです。
しかし、プレデターの武装化は、技術的な問題、資金面の問題、政府をはじめとする官僚組織、さらには新しいものへの拒否反応を示す軍人などといった、数々のハードルに阻まれます。
クラークは、「プレデターは技術的にまだ発展途上ではあるが、最大の欠陥は陸海空軍の対立関係にある」と結論づけた。「プレデター最大の問題は、明らかに政治的なものである」とクラークはフォーグルマンへの報告書に書いた。「陸軍は、先進概念技術実証をおこなったあとでプレデター計画を奪われたことにいまだに腹を立てている。陸軍司令官らをきちんとサポートする能力が空軍にないことを立証し、プレデター計画を自分の手に取り戻す、あるいは、ハンター計画(訳注:陸軍による無人機開発計画)への資金提供を復活させる、というのが彼らの計画かもしれない」。(p.141)
その一方で、開発チームは、プレデターを、着実に実用化へと近づけていきます。
ビッグサファリの哲学は、「最小限にして充分なものを」「既成品を活用せよ」「情報は知る必要のある人間だけに」「修正せよ、開発すべからず」「あったらいいものではなく必要なものを」といったモットーやキャッチフレーズや警句に表れていた。(p.144)
そうした中、2001年9月11日、アメリカ本土へのいわゆる同時多発テロが発生し、武装したプレデター=無人暗殺機=の実用化が、一気に進んでいくことになります。
本書の邦題は『無人暗殺機ドローンの誕生』ですが、原題は《PREDATOR – THE SECRET ORIGINS OF THE DRONE REVOLUTION》です。無人機を意味する drone の revolution の知られざる始まりはプレデターである−アマゾン・ドット・コムやグーグルが無人航空機による無人配送システムを計画しているとのニュースは記憶に新しいところですが、インターネットやGPSがもともとは軍事目的で開発されたように、プレデターで培われた技術も、近い将来、われわれの生活を支えるものの一つになるのかもしれません。
蛇足ながら、本書がすごいと思ったのは、巻末に30ページに及ぶ「ソースノート」が付されていることです。参考文献リストとは別に、本書で明らかにされた事実の根拠が、丁寧に記されています。こういうのを見ると、アメリカはやっぱりすごいと思います。