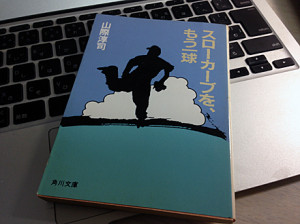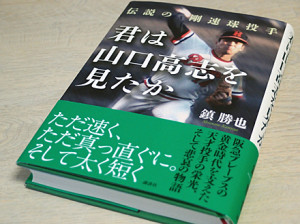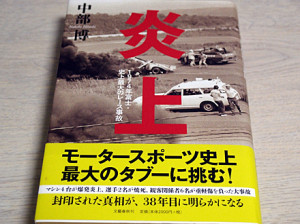2014年11月 の投稿一覧
スローカーブを、もう一球(山際淳司、角川文庫)
Posted by 大熊 一精 on 2014年11月30日(日) 06:39
スローカーブを、もう一球(山際淳司、角川文庫)
昭和60年2月10日初版発行。現在は電子書籍(Kindle)版も出ています。
もしかすると作品以上に言葉のほうが有名になった「江夏の21球」をはじめ、8本のノンフィクションが収録されている短篇集。何度も読んでいる本なのですが、山口高志の評伝を読んだら「江夏の21球」を思い出して(「江夏の21球」の舞台は山口高志の全盛期直後です)、ひさしぶりに読んでみました。
収録されている8本の短編のうち、野球をテーマにしたものは、半分の4本です。なかでも私が好きなのは、本のタイトルにもなっている「スローカーブを、もう一球」のラストシーン。進学校である高崎高校の、合理的すぎるほどに合理的な主戦投手の物語の、この、ラストの数行は、文字しか書いていないのに、目の前に映像が見えてきます。
好きなシーンの次点は、これまた高校野球を描いた「八月のカクテル光線」の、これまたラストシーン。山際淳司さんは、スポーツを描くにあたって当時としては画期的な手法を用いたことで、この本で日本ノンフィクション賞を受賞されたわけですが、あらためて読んでみると、映像を切り取るのが巧かったのだなと感じます。
有名な「江夏の21球」は、やっぱり、衣笠がマウンドに行く場面でしょう。
電子書籍版もあるので、未読の方は、この機会に、ぜひ!
伝説の剛速球投手 君は山口高志を見たか(鎮勝也、講談社)
Posted by 大熊 一精 on 2014年11月29日(土) 06:58
伝説の剛速球投手 君は山口高志を見たか(鎮勝也、講談社)
2014年10月刊。
帯に書かれた言葉は「阪急ブレーブスの黄金時代を支えた天才投手の栄光、そして悲哀の物語」なのですが、読後感に「悲哀」はなく、むしろ、清々しさが残りました。見る角度によっては、酷使されて登板過多の結果、選手寿命がきわめて短くなってしまった投手の物語、なのかもしれませんが、やるだけのことはやったうえで現役を引退し、その後も後進の育成という形で野球の現場に関わり続けている山口高志の人生は、記録にあらわれるキャリアから受ける印象よりは、はるかに幸福であるように思えます。
「タカシ、そんなフォームやったら体がもたん。必ずケガするぞ」
「フクさん、ありがとうございます。でも自分は太く短くでいいです」
「アホか、プロは長くや」
福本は山口にいずれ訪れる最後をケガがもたらすであろうことを悟っていた。
「言うた通りになった。ギッコンバッタンの影響で腰がパンクした。ハードな投げ方やからそうなる。ええ時期はたった四年。もったいなかったなあ」
引退を惜しんだ。
(p.220)
「君は山口高志を見たか」と問われれば、私は、小学生の頃に、テレビで見ました。ただ、当時はプロ野球のテレビ中継といえば巨人戦、そしてこちらは小学生ですから、なんとなくの記憶しか残っていませんが(日本シリーズでは足立がすごかった、とかね)、それでも、当時のおぼろげな記憶を手繰り寄せれば、山口高志の印象だけは強烈に甦ってきます。
いうまでもなく、当時のテレビ中継やスポーツニュースにおいて(そもそもスポーツニュースなるものも現在ほどにはなかったように思うのですが)、球速表示などという概念は存在しておらず、「大谷はすごい、なんてったって160kmだ」みたいな語られ方は、しようがなかったわけです。
そういう中で、山口高志の印象だけが(当時小学生だった私ですら)残っているのは、なんだかわかんないけど毎日投げていた、というのと、この本の中で繰り返し言及されている特異なフォームゆえ、なのでしょう。もちろん、投げる球は猛烈に速かったはずなのですが、まさに「剛速球」の「剛」といったイメージの体の使い方が、その速さ、すごさを、記憶の中で増幅させているのだと思います。
ニッポン超越マニア大全(北尾トロ、文庫ぎんが堂)
Posted by 大熊 一精 on 2014年11月25日(火) 19:46
ニッポン超越マニア大全(北尾トロ、文庫ぎんが堂)
2014年11月刊。
登場するのは、さまざまな分野の「マニア」である24人。マニアな人々にインタビューする著者は、彼らに感心しつつも少し呆れる、でもけっしてバカにすることはしない、という、絶妙な立ち位置を保っているのが素晴らしい。
素晴らしいのは登場するマニアの方々も同様で、その多くは何らかのコレクターであるのですが、50歳を過ぎてから趣味に走った方も、子供の頃からマニア道まっしぐらの方も、職業生活はしっかりとやっていらっしゃる(まあ、そうでないと、金銭的に続かない、という面も大きいとは思いますが)。さらに素晴らしいのは、多くの方は妻子がいらして(この本に登場する24人のうち女性は1名のみ)、ご家族の理解を得ている(らしい<中には「あきらめられている」らしき方も見受けられますが)。
上の写真にあるように、帯には4人のマニアが紹介されていますが、私がいちばん気になったのは、ここには載っていない、消防車が好きで古い消防車(ホンモノ)を9台も所有している方でした。この方は小学生の頃からの消防車好き。なぜ他の自動車(たとえばパトカー)ではなく消防車だったのか?との問いかけに対しては《緊迫感かな。火事を消し止めたり誰かを助けるために働くクルマでしょ。緊急事態が発生し、サイレンを鳴らして現場に行く。その姿がカッコよかったんですよね。》と答えていらっしゃる。その感覚はわかるようなわからないような、だけれども、明確な言葉にできるのが素敵です。
1964年のジャイアント馬場(柳澤健、双葉社)
Posted by 大熊 一精 on 2014年11月24日(月) 20:04
1964年のジャイアント馬場(柳澤健、双葉社)
2014年11月刊。600ページ近い大作です。著者は『1976年のアントニオ猪木』(文藝春秋、文春文庫)、『1985年のクラッシュ・ギャルズ』(文藝春秋)などでお馴染みの柳澤健氏。これは読むしかない!
1964年の、と銘打たれてはいますが、1964年の出来事だけが書かれているわけではなく、ざっくり言えば、生まれてからこの世を去るまでの、ジャイアント馬場の伝記です。その一生を語るのに600ページ近い分量が必要だったのは、プロ野球選手からプロレスラーに転じた直後のジャイアント馬場について語るためには、当時の米国のプロレス事情を説明しなければならなかったからです。昭和30年代に日本人が(プロレスというやや特殊な世界の出来事ではありますが)米国へ出て行くとはどういうことなのか?
著者は、アメリカ大陸に渡って、当時を知る人々へのインタビューを行い、米国内にしかないであろう多数の一次資料を発掘することで、事実を拾い集めていきます。
では、なぜ、1964年なのか?
1964年と聞けば、東京オリンピックに東海道新幹線の開業がすぐにイメージされますが、プロレス界(というより当時の感覚では日本のエンターテイメント界なのでしょう)にとっては、力道山の死の翌年です。力道山が刺されて死んだとき、馬場はアメリカに滞在していました。そして、当時の馬場=日本国内の認識は海外武者修行中の若手レスラー=は、アメリカで、とんでもないギャラをもらえる大スターに成長していました。
大スター、すなわち、大金を稼ぐことのできる人間のまわりには、たくさんの人々が群がってきます。若くして大金を手にしたスターは、そうした人々に足を引っ張られて転落していく…というのが、よくある構図ですが、馬場は違いました。
馬場は一瞬のうちに自分を取り巻く状況を把握する。
なるほど、それでわかった。日本プロレスにクビを切られたからこそ、東郷は自分と一〇年に及ぶ長期契約を結ぼうとしたのだ。俺を人間扱いしなかったグレート東郷と、力道山が死んだ時に連絡をくれなかった日本プロレスは、いまやなんとかしてこの俺を手に入れようと必死になっている。
悪くない状況じゃないか?
(p.382)
これが、1964年のジャイアント馬場です。
子供の頃からずっと、大きな体に向けられる興味本位な視線にコンプレックスを感じていた馬場正平が、《職業として、生きていくための最良の手段として、プロレスを選択》(p.76)して、プロレス入門から4年余という年月の間に、ここまでの存在になれたのはなぜか?
それは、馬場が非常に優れたアスリートであったからです。著者は、アスリートとしての馬場正平の姿を、さまざまな角度から描いています。馬場は、非常に高い身体能力がベースにあって、そのうえで、プロレスといういわばショービジネスの世界で生きていくにはどうすればよいのかを、冷徹に観察したのです。職業として(≒かならずしもやりたいわけではないけれど)プロレスを選んだ馬場は、自分が生きていくためには、自分が属している世界のルールを学ぶしかなく、そして馬場にはそれができた。そうやって、馬場は、トップスターへの道を歩んでいくのです。
でも、この本は、けっしてジャイアント馬場礼賛ではありません。終盤の、猪木・新日ブーム(私はまさにこの世代です)以後の馬場の評価については、かなりネガティブです。そうしたことも書かれていることは、この本の信頼度を高さの表れでもあるといえましょう。
『釧路炭田 炭鉱(ヤマ)と鉄路と』石川孝織(水公舎)
Posted by 大熊 一精 on 2014年11月21日(金) 19:24
『釧路炭田 炭鉱(ヤマ)と鉄路と』石川孝織(水公舎)
2014年9月刊。
北海道新聞釧路版に連載された64編のエッセイ+貴重な写真を、1本あたり見開き2ページで収録した第1部「炭鉱と鉄道」と第2部「炭鉱の仕事とくらし」に、1ページに2枚ずつの写真を掲載した「写真で見る炭鉱と鉄路」(約50ページ)を合わせた200ページ近い一冊。これが1200円とは、申し訳なく思えてくるほど、貴重な資料集です。
64編のエッセイは、著者の個人的感慨などの類ではなく、釧路周辺の炭鉱で働いていた人、炭鉱とともに生活していた人たちの証言を、丹念に拾って、当時の暮らしぶりを文字上で再現したものです。登場人物の大半は高齢者であり、80代以上の方も少なくありません。失礼ながら、こうした証言を集めるには、ギリギリのタイミングだったかと思われます。
それだけでも素晴らしい仕事ですが、この本そのものが、じつに丁寧に作られています。釧路炭田といわれても、どこのことなのか、私には正直さっぱりわからないのですが、目次の直前のページに掲載された「釧路炭田の主な炭鉱(1960年代)」の地図をはじめ、当時の鉄道路線図などが多数掲載されており、本文の内容の理解を助けてくれます。
古いカラー写真もたくさん載っています。
比較的有名な釧路臨港鉄道(太平洋石炭販売輸送)や雄別鉄道(湧別炭鉱鉄道)のほかに、尺別鉄道(尺別炭鉱専用鉄道)という知られざる鉄道の記録(文字、写真)も多数掲載されています。尺別炭鉱と浦幌炭鉱とをつないでいた尺浦隧道(延長約6km)を走る小さな機関車(パンタグラフ付き)の写真なんて、さりげなく掲載されてますが、衝撃写真ではないかと思います。
筑豊に比べると、北海道の炭鉱に関する資料や展示は(少なくとも一般人の目に容易に触れるものは)少ないと感じていただけに、こうした本が完成して市販されていることは、とても嬉しいことです。
amazonは現時点では在庫切れ表示なので、奥付の情報を以下に転記しておきます。
釧路炭田 炭鉱と鉄路と 著者 石川 孝織
発行者 釧路市立博物館友の会(釧路市春湖台1-7 釧路市立博物館内)
発行所/印刷製本 水公舎/(株)藤プリント(釧路市栄町10-3 TEL 0154-22-9311)
※私は書泉グランデで買いました。
『ぼくは眠れない』椎名誠(新潮新書593)
Posted by 大熊 一精 on 2014年11月19日(水) 19:19
『ぼくは眠れない』椎名誠(新潮新書593)
2014年11月刊。
およそ不眠症などという言葉が似合わない椎名誠さんの不眠症睡眠薬常用告白と、眠りに関する本をたくさん読んだ椎名さんの睡眠不足考察。椎名さんの語り口は、いつものごとく、やわらかくて軽いのですが、書かれている内容は、けっして軽くはありません。
「35年間、不眠症」(帯のキャッチコピー)といっても、椎名さんは、365日×35年=12,775日にわたって毎日眠れていないわけではなく、何の苦もなく寝付けて、朝までぐっすりと眠れる、という日も、ときにはあります。それはなぜなのか?そうした場面ではいかなる条件が睡眠を快適にしているのか?等々の考察は、とても興味深いものばかりです。
サラリーマンをしているときと、会社を辞めてフリーのモノカキになってからの「眠り」で一番ちがったのは「逆算」する必要がないということだった。(中略)武蔵野の自宅から銀座にある会社まで、当時は乗り換え三回、一時間二十分はかかった。それを逆算して家をでることになる。そこから逆算して起床時間がおおよそ決まってくる。さらに逆算して寝る時間がそれなりに一定してくる。(中略)睡眠生活を中心にしたリラックスにはこの適度な心身に対する大波、小波とき荒波のまじった生活のリズム感、というようなものが案外大事なのかもしれない。そういうコトに気づいたのはサラリーマンをやめてもうだいぶたってからだった。(p.41-42)
私はこの箇所を読んで、へんな話ですが、安心しました。私自身はサラリーマンを辞めてから12年余の間、フリーとは言いながら、毎朝決まった時刻にどこかへ行かねばならない身分だった時期と、そうでない時期とがあって、前者の時期には「決まった時刻に行かねばならない」ことを苦痛に感じるときもあるのに、後者の時期になると「決まった時刻に行かねばならない場所がない」ことが苦痛になります。椎名さんの言う「逆算」をする必要がないことを気楽に思えるのは最初だけで、やがて逆算できないことが心身の不調につながってくるのです。
でも、安心している場合ではありません。
サラリーマンを辞めた椎名さんは、いわゆる夜型に生活時間をシフトさせることで、作家としての生活のリズムを整えていくものの、椎名さんの仕事には旅が欠かせない。旅先では昼間の活動が中心になるから、夜中に活動して明け方に寝るというわけにもいかず、夜はちゃんと寝るものの《夜中の二時とか三時頃に目を覚ましてしまうのだ。本を読んだりして対策するが、真夜中にはなかなか集中して本を読む気にはならないものだ。そこで知らない旅館やホテルの一室で悶々とするのである。(中略)そういう恐怖(大袈裟に聞こえるだろうが、精神的にはまさに恐怖なのである)を乗り越えるためにこれは「睡眠薬」がなんとしても必要だ、と考えるようになった。》(p.61)。
そうなんです。眠れないから昼間に眠くなる、とかなんとかよりも、眠れないことそのものが怖くて、精神的にはまさに恐怖なんです(これは私もわかります)。
睡眠薬と聞くと怖いイメージがありますが、眠れないことへの恐怖を抱き続けるぐらいなら睡眠薬を(医師の正しい処方のもとに)服用したほうがよいのだ、という話が、上の引用箇所に続けて、著者自身の体験談とともに語られていきます。
【目次】
1 はじまりは唐突にやってきた
2 勤めをやめるか、どうするか
3 ライオンのように眠りたかった
4 見知らぬ女が押しかけてきた5 なぜ眠る必要があるのだろうか
6 こころやすらかに寝られる場所は
7 睡眠薬は脳に何をしているのか
8 ポル・ポトの凶悪にすぎる拷問椅子
9 イネムリが人生で一番ここちよい
10 睡眠グッズはどれほど効くか
11 やわらかい眠りをやっと見つけた
『インターネット的』糸井重里(PHP文庫)
Posted by 大熊 一精 on 2014年11月17日(月) 17:58
『インターネット的』糸井重里(PHP文庫)
糸井重里さんの『インターネット的』は、2001年7月にPHP新書として刊行された名著です。名著であるにも関わらず長らく絶版になっていましたが、このたび(2014年11月刊)、文庫で再登場しました。文庫化にあたって、「文庫版のまえがき。」と「続・インターネット的」が付け加えられています。
著者は、この本で、インターネットの登場によって、インターネット的な社会が作られていくであろう、インターネット的な人間関係が構築されていくであろう、生産者と消費者の関係はインターネット的な関係に変わっていくであろう、といったことを、インターネット「的」と表現したのですが、2001年時点では、これはいまいち受け入れられなかったようです。
でも、私にとっては、この本は、サラリーマンを辞める決断を後押ししてくれた、大事な本です(私は2002年3月末で新卒以来お世話になっていた会社を辞めました)。その本が十余年の月日を経て陽の目を浴びているのは、とても嬉しいことです。
文庫版のあとがきに当たる「続・インターネット的」と題した章の中で、著者は、新書版刊行当時に『インターネット的』が読まれなかった理由を《この本には「インターネットは儲かるぞ」って書かれていない》ことだとしています。
たしかに、インターネットが生み出す新しいビジネスチャンス!のようなことは、この本には、出てきません。それでも、私は、当時、この本から、多くのことを学びました。
今回、文庫版が出た(新千歳空港の紀伊國屋書店の店頭でたまたま発見して購入した)ことに伴って読みなおしてみて、ああそうか、これはこの本に書いてあったことなのか!と気付かされたことが、たくさんありました。「わからないことは言わない」「とにかく褒める」「自分の市場を持つ」etc.…それ自体はノウハウではないものの、何かを行なううえでの基礎になることは、たくさん書いてあるのです。
もうすぐKindle版も出るようです。
【目次】
文庫版のまえがき
プロローグ なぜいま、インターネット的なのか
第1章 インターネット的
第2章 インターネット的でどうなる?
第3章 工業化社会からインターネット的社会へ
第4章 インターネット的思考法
第5章 インターネット的表現法
第6章 インターネットの幻想
第7章 消費のクリエイティブを!
エピローグ 「インターネット的」時代のゆくえ
続・インターネット的
『「本が売れない」というけれど』永江朗(ポプラ新書046)
Posted by 大熊 一精 on 2014年11月16日(日) 06:02
『「本が売れない」というけれど』永江朗(ポプラ新書046)
2014年11月刊。
本が売れないというけれど、書店がなくなっているのは事実だけれど、ブックオフの売上や図書館での貸出数をみれば、読書人口は減っていないのだから、根本的な問題は所得の減少という、つまりは本に限らず他の業界にも共通した問題が背景にあるのに、ことさら本だけを特別扱いして考えるのはちょっと違うんじゃないの?そもそも「活字離れ」って、ずいぶん前から言われてるじゃないですか。業界的に景気がよかった頃を基準にして考える、いや、考える前に思考停止の状態になってるんじゃないの?…といったことが、著者の経験と統計データを元に綴られています。
ものすごく乱暴にまとめてしまえば、外部環境のせいにしても始まらない、出版業界ないし書店も(そんなことできないなどと言わずに)できることを(努力して)やっていきましょうよ、という話なのですが、かたやで本という商品の特殊性(たとえば流通形態)について丁寧な説明もなされており、本好きな方、本に興味のある方は必読です。
【目次】
プロローグ ベストセラーは出したいけれど
第1章 日本の書店がアマゾンとメガストアだけになる日
第2章 活字ばなれといわれて40年
第3章 「街の本屋」は40年間、むしられっぱなし
第4章 「中くらいの本屋」の危機
第5章 電子書籍と出版界
第6章 本屋は儲からないというけれど
第7章 「話題の新刊」もベストセラーもいらない
エピローグ どこから変えるべきか
『炎上 1974年富士・史上最大のレース事故』中部博(文藝春秋)
Posted by 大熊 一精 on 2014年11月11日(火) 09:27
『炎上 1974年富士・史上最大のレース事故』中部博(文藝春秋)
2012年4月刊。前回取り上げた『日本のモータースポーツ黎明期物語 砂子義一伝説』から時代が下って、日本国内でもプロフェッショナルによって行われる自動車レースがビッグイベントとして成立するようになった時代の話です。
ひとつのレース大会で、ふたりのレーシングドライバーが事故死したことはある。一九九四年(平成六年)のF1グランプリ第三戦サンマリノ・グランプリで、このときは予選と決勝でそれぞれ死亡事故が発生した。したがって同時にふたりのレーシングドライバーが命をうしなったわけではない。(中略)自動車レースの世界史で、ひとつの事故で、ふたりのレーシングドライバーが事故死したレースは、ほかにないのであった。そのことで自動車レースの世界史に記録されるべき事故だった。しかもそれが、当時の日本最高峰の自動車レースで発生したことは、日本のレースファンの心にえぐるような衝撃をあたえた。
(p.13)
この事故では、事故の原因を引き起こしたとされる出場選手(レーシングドライバー)の一人が、業務上過失致死傷罪の疑いで書類送検されています(のち不起訴)。レース中の事故というのは、普通に考えれば偶発的でやむを得ないことであり、それが罪に問われるというのは、なんとも妙です。
それがゆえに、なのでしょう。この事故については、映像が残っていないなど、これだけの大事故であるにも関わらず、きちんとした検証が行われていない。少なくとも、現在、検証できるような資料が残されていない。
なぜ、こんなひどい事故が、おきたのだろう。
長い間そんな疑問を抱いていた著者は、何年もの時間をかけて、丹念に、資料を集め、レースに出場していたレーサーから粘り強く証言を引き出し、事故の全容を解き明かしていきます。
この本は、労作かつ貴重な記録であると同時に、謎解きの本でもあります。
『日本のモータースポーツ黎明期物語 砂子義一伝説』(kindle版)
Posted by 大熊 一精 on 2014年11月8日(土) 10:56
『日本のモータースポーツ黎明期物語 砂子義一伝説』
最初は金持ちの道楽だったカーレースの世界に、自動車メーカーが会社として参戦し、そしてプロのレーシングドライバーという新しい職業が生まれていく−という過程を、日本のレーサーの草分けである砂子義一の生涯を通じて描いた作品です。
と、さらっと書きましたが、私は砂子義一なる人物のことは、名前すら知りませんでした。この本の冒頭に登場する「日本グランプリ」という、F1とはまったく無関係なカーレースのことも、この本で初めて知りました。第1回日本グランプリの開催は1963年、鈴鹿サーキット開業の翌年のことです。
第2回日本グランプリにプロのレーシングドライバーとして参加した砂子義一は、カーレーサーになりたくてなったわけではありません。そもそも、1937年生まれの砂子義一の前には、プロのレーシングドライバーなどという職業は存在していなかったのですから、なりたいと思うはずもありません。
そんな時代に、工業高校を出てバイクメーカーに就職した砂子義一が、プロのレーシングドライバーになっていく経緯は、現在からみれば驚くほど牧歌的です。
この作品(電子書籍)は、著者による砂子義一氏へのロングインタビューを中心に、著者がこつこつと集めた資料や、砂子義一氏提供による貴重な写真を、出版社を使わずにまとめたものです。旧来型の紙の本であれば費用面での高いハードルがあった自費出版が、電子書籍の登場によって容易になり、こうして成果物として多くの人の目に触れられる形になりやすくなったことは、素晴らしいことです。
ちなみに、amazonプライム会員だと、無料で読めます(が、私は280円で購入しました…このブログを書くにあたってamazonの当該ページを見直してから、じつは無料で読める=読めた=のだと気づいたのでした)。