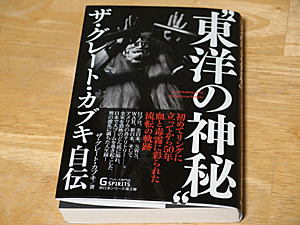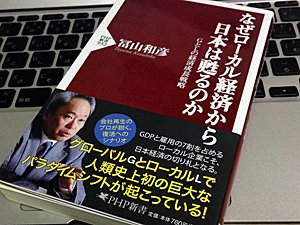2014年10月 の投稿一覧
『東洋の神秘 ザ・グレート・カブキ自伝』(辰巳出版)
Posted by 大熊 一精 on 2014年10月30日(木) 20:15
『東洋の神秘 ザ・グレート・カブキ自伝』(辰巳出版)
帯に曰く「波乱に満ちた人生録!」とありますが、スキャンダラスな話は、ほとんど、出てきません。本人の周辺では、いろいろ、起こっているのですが(とりわけ終盤に出てくるSWSのあれこれはキツいものがありますが)、語り口がさらっとしていることに加え、著者(ザ・グレート・カブキ)は混乱の渦中には身を置くことなく、さりとて保身に走って慌てふためくでもなく、つねに、自分の立ち位置、あるいは自分の役割を冷静に、まるで他人のように自分自身を見つめていることもあり、デビュー50年のプロレスラーの自伝にこんな言葉を使うのは妙だと思いつつも、読後感は「さわやか」です。
もちろん、わかりやすいエピソードは、たくさんあります。
ゴッチは新日本プロレスのファンやレスラーから”プロレスの神様”と崇め奉られたが、俺は猪木さんによるイメージ戦略の賜物だと思っている。俺はゴッチのことを強いとはとても思えなかった。(p.60)
馬場さんは俺にも5年契約の話をしてきたが、それは断った。しかし、馬場さんは輪ゴムで止めた札束を紙袋に入れて、俺の前に出してきた。俺も全日本には貢献してきたという自負がある。しかし、ギャラの面ではまったくと言っていいほど、いい扱いを受けてこなかった。それが団体がピンチに陥り、今更金を積んできたのである。俺の目の前で馬場さんは「よく見ろ」と言いながら、懐中電灯で金の入った紙袋の中を照らした。(p.187)
こうしたことを堂々と言えるのは、著者には、自分で自分の人生を作り上げてきたという自信があるから、であり、その自信の土台には、磨き続けてきたプロレスの技術と、絶えず考え続けてきたお客さんを喜ばせる工夫がある、ということが、読み進めるうちに、わかってきます。
私にとっては、フリーランスで生きていく、うまく世の中をわたっていくためにはどうすべきか?の、いい教科書になりました。まさかこの本をこういうふうに読むことになるとは思いもしませんでしたが、だから読書は楽しいのです。
『日本代表はなぜ敗れたのか』湯浅健二+後藤健生(イースト新書036)
Posted by 大熊 一精 on 2014年10月29日(水) 17:09
『日本代表はなぜ敗れたのか』湯浅健二+後藤健生(イースト新書036)
今年(2014年)の6月から7月にかけて開催されたワールドカップブラジル大会について、湯浅健二さんと後藤健生さんという大ベテラン(お二人とも1952年生まれ)が対談した本です。
タイトルは「日本代表は」ですが、内容は、日本代表の話にとどまらず、ブラジル大会全般に及んでいます。あのブラジルの惨敗や、ドイツの優勝についてはもちろんのこと、ベルギーやナイジェリアの話まで出てきます。
ベルギー?ナイジェリア?そんなこと言われても、わかんないし…と言いたくなるところですが、ベルギーやナイジェリアがどんなチームだったのかを知らなくとも楽しめるのは、湯浅健二さんと後藤健生さんの、長い経験や教養をベースにした語り口があるからです。
教養がありすぎて(?)、ときどき、湯浅さんが、日本の国民性を根拠に日本代表のプレーについて語ろうとすると、後藤さんが、サッカーのことはサッカーの中だけで話をしましょうよとばかりに反論して、けっして「なあなあ」で終わらせないのも、この本の面白さです。
同じお二人の対談本は、前回のワールドカップ(2010年の南アフリカ大会)の直後にも、出版されました(『日本代表はなぜ世界で勝てたのか?』アスキー新書161)。この本には、じつに印象深い記述があります。
後藤 (注:ワールドカップ直前の韓国戦での敗戦について)試合後、岡田武史の口から「進退伺い」が飛び出したわけだけれども、あんなジョークが言えるようになったのだから、岡田も安心できたのだろうと思ったね。
湯浅 あそこで笑ったのは、私たちと大住良之さんの3人だけだったわけだけれども。
(『日本代表はなぜ世界で勝てたのか?』p.011)
当時、この「進退伺い」は、翌日に大騒ぎになり、岡田武史監督(当時)が「あれはジョークだった」と言ったのがさらに批判を浴びる、という顛末になったのですが、ジョークをジョークと理解した人もいたのだ−ということを、この本で初めて知りました。
そんなこともあって、同じお二人による同じコンセプト(ただしタイトルは正反対)の対談本を、大いに期待しながら手に取ったのですが、期待をはるかに上回る面白さでした。分量も、前回よりも、かなり増えています。
今回の対談の最後は、こんなふうに締めくくられています。
湯浅 4年後のロシア大会でも、またやりましょう。
後藤 今回、日本代表が負けてしまったから、この本売れるかなあ。次はないかもよ。
湯浅 そこは我々も「売るための意志」を持ち続けるべきじゃないですか。
(『日本代表はなぜ敗れたのか』p.283)
次はないだって!?…それは困ります!4年後のロシア大会後も、この対談を読みたい!だから、みなさん、この本を買って読みましょう!と、応援する気持ちから、この本を紹介させていただきました。
『青函連絡船 海峡の記憶』白井朝子(舵社)
Posted by 大熊 一精 on 2014年10月28日(火) 19:36
『青函連絡船 海峡の記憶』白井朝子(舵社)
大型の写真集です。2000年2月刊。国鉄広報部専属カメラマンを経てフリーの写真家になった白井朝子さん(函館生まれ、札幌育ち)による青函連絡船の記録は、JR北海道の協力の下で撮影されたものゆえ、乗客目線というよりは乗員の目線です。
いや、乗員、というより、船乗り、といったほうが、適切かもしれません。
描かれているのは、5000トンを超える大きな船を、津軽海峡の荒波の中、安全に航行させるための男たちのドラマ…いやいや、そこにドラマチックな出来事はないのですが、でも、動かない写真なのに、そこから伝わってくるのは、多くの乗客の命を預かる男たちの息吹です。
この素晴らしい写真集は、残念ながら、すでに絶版となっていますが、札幌駅エスタ11階(JRタワープラニスホール)で11月3日まで開催中の「海峡が見た夢~青函連絡船から新幹線へ 世紀を越えて~」展の会場にて、白井朝子さんがご自身の手で販売されています。
きわめて個人的な話になりますが、北海道には地縁血縁何もなかった私が、いま札幌で暮らしているのは、学生時代に上野発の夜行列車と青函連絡船を乗り継いで北海道に渡り、北海道を旅したことがきっかけです。学生が飛行機に乗るなんて考えられなかった時代(現在はむしろ飛行機のほうが運賃が安いのですが…)、初めての北海道が二度目の北海道になり、やがて三度目、四度目となっても、往復の足は、いつも、夜行列車(もちろん寝台なんか使いません)と、青函連絡船でした。この写真集のページを繰るたび、当時の記憶が、ありありと、蘇ってきます。
『銃・病原菌・鉄』ジャレド・ダイアモンド(草思社文庫)
Posted by 大熊 一精 on 2014年10月27日(月) 22:40
『銃・病原菌・鉄』(上・下)ジャレド・ダイアモンド/倉骨彰=訳(草思社文庫)
原著は1997年刊、邦訳は2000年に単行本として刊行された後、2012年に文庫化されました。原題は “GUNS,GERMS,AND STEEL〜The Fates of Human Societies”、日本語版には「一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎」という副題が付されています。
ヨーロッパ人が持ち込んだ病原菌の犠牲になったアメリカ先住民や非ユーラシア人の数は、彼らの銃や鋼鉄製の武器の犠牲になった数よりもはるかに多かった。
(プロローグ)
なぜ地球上の各地に現在のような人口分布、そして富や権力の偏在が起きたのか?を解き明かすうえで、じつは、病原菌の存在と進化は、欠かすことのできない要素であった−といった話は、この本の第11章(文庫版では上巻の最終章)で、詳しく説明されています。
人間の死因でいちばん多いのは病死である。そのため、病気が人類史の流れを決めた局面も多々ある。たとえば、第二次世界大戦までは、負傷して死亡する兵士よりも、戦場でかかった病気で死亡する兵士のほうが多かった。戦史は、偉大な将軍を褒めたたえているが、過去の戦争で勝利したのは、かならずしももっとも優れた将軍や武器を持った側ではなかった。過去の戦争において勝利できたのは、たちの悪い病原菌に対して免疫を持っていて、免疫のない相手側にその病気をうつすことができた側である。
(第11章 家畜がくれた死の贈り物)
それにしても、「人間である」という点では同じなのに免疫のある側とない側とが存在していたのは、なぜなのか?あるいは、現代のように飛行機で人やモノが行き来しているわけではなかった時代に、病原菌はいかにして生き延びて、遠く離れた土地にまで勢力を広げていったのか?…そうした数々の疑問に対し、著者は、学問の枠を超えた知見を総動員して、謎解きを進めていきます。
文庫本とはいえ、上下巻それぞれ約400ページ、いくつかの図表は挿入されているものの、基本的には文字がびっしり、しかも最初から順番に読んでいかないと理解しづらい、という具合に、なかなか手強い本ではありますが、わかりやすい日本語訳で綴られているため、ぱっと見の印象よりは、はるかに読みやすいです。
電子書籍(Kindle)版も出てます。
『僕たちは就職しなくてもいいのかもしれない』岡田斗司夫(PHP新書950)
Posted by 大熊 一精 on 2014年10月25日(土) 09:31
カバーが2枚(二重に)ついてます。
内容は、著者が、同志社大学で行なった講演をベースにしています。
タイトルといい、大学での講演が元になっていることといい、これから社会に出る人をはじめとする若者向けの本、との印象も受けますが、そうした実用書的な読み方だけでは、もったいないです。この本は、読者の年齢に関係なく、考えるヒントになり得る、一種の社会批評です。
タイトルが意味するのは、現在は以前と違って会社が人を雇わなくなっている、そしてその傾向はこれからますます強くなっていく(それがなぜか?も本の中で丁寧に説明されています)、だから就職(就活)が厳しいのは当然でしょう、そういう中でわざわざ厳しい世界に入っていかなくとも、別の方法もあるんじゃないの?といったことなのですが、その根底にあるのは、価値観の大転換です。
いわゆるバブル期まで「標準的」と考えられていた生き方は、もはや通用しなくなっているのに、それを追い求めるからつらくなるんだよ、というのが、著者の主張です。
こうした考え方は、若者だけではなく、バブル期を体験していて現在の日常が苦しいと感じている世代にとっても、自分自身を見つめ直すきっかけになると思います。その意味では、表紙(カバーのうち上についているほう)に書かれた《就活や会社生活に疲れきったすべての日本人に》というキャッチコピーは、けっして大げさではありません。
『金哲彦のはじめてのランニング 運動ゼロからレース出場まで』金哲彦(朝日新書449)
Posted by 大熊 一精 on 2014年10月22日(水) 21:27
『金哲彦のはじめてのランニング 運動ゼロからレース出場まで』金哲彦(朝日新書449)
上の写真は、礼文島で毎年初夏に開催されている「最北フラワーマラソン」の今年(2014年)の大会の、スタート直前の様子です。私も、このスタート地点に、出場者の一人として、立っていました。
私は礼文島の民宿海憧に、長年にわたってお世話になっています。礼文島で、毎年、フラワーマラソンなる行事が開催されていることは、以前から知っていました、が、マラソンの趣味などはまったくなく、むしろ、街なかをジョギングしている人を見かけると「よくやってるなあ…」と(まったく他人事として)見ていたぐらいでした。
だのに、なぜ…フラワー「マラソン」といっても5km(または10km)であれば、まあ、なんとかなるかなと、突然、出場を決めてしまいまして、とりあえずランニングシューズだけ買って、ようやく雪が消えたばかりの自宅の近所を走りはじめた頃、たまたま入った書店の店頭で目にしたのが金哲彦のはじめてのランニング 運動ゼロからレース出場まで (朝日新書)。
はじめてのランニング、しかも「運動ゼロから」!
そうはいっても、ねえ…本当に運動ゼロでいいの?…そんなわけないよね…と、半信半疑で、目次を見てみれば、
「外に出よう、歩いてみよう」
「まずは着替えて外に出る」
「まずは歩きましょう!」
お!これなら、できるかも…できそうだ!!
この本の著者である金哲彦さんが、一般人向けランニング講座の第一人者である、ということは、この本を手にするまで、知りませんでした。競技スポーツの第一線で活躍されていた方は、もともと運動好き&運動が得意であるから、超初心者には難しい指導を平気でしてくるんじゃないか…といった先入観を抱いていたのですが、この本は、優しい(易しい)のです。
本の副題は「レース出場まで」ですが、204ページまであるこの本の中で、「大会に出場しよう」という見出しが登場するのは、177ページです。つまり、本全体の9割近くは、「レース出場」以前の話なのです。
礼文島のフラワーマラソンが終わってからは、大会に出場することもなく、タイムや距離を気にすることもなく、ときどき、ランニングを楽しんでいます。そうしたことを意識しないからこそ、続けられているのだと思います。それは、すべて、この本のおかげです。
『盗まれた都市』西村京太郎
Posted by 大熊 一精 on 2014年10月19日(日) 09:05
『盗まれた都市』西村京太郎
今回は、絶版本です。
古い頭で考えると、書評に絶版本を取り上げることはないのでしょう。でも、現在は、昔と違って、よほどの希少本でない限り、インターネットで探せば、すぐに手に入れることができます。古書店を探しまわるようなことをしなくとも、手元でポチれば手に入るのですから、便利な時代になりました。
私事になりますが、先日、西村京太郎さんのお話を、目の前でお聞きする機会に恵まれました。それに先立って、西村京太郎作品を集中的に読みました(西村京太郎さんの過去作は多くが電子書籍化されているので、ポチッとやるだけで手軽に読めます)。その大半は、十津川警部を主人公とした「◯◯(地名または鉄道路線名)殺人事件」です。
そんなとき、Facebookで教えていただいたのが『盗まれた都市』でした。いわく、西村京太郎は十津川警部の殺人事件だけじゃないですよ、『盗まれた都市』は古い作品だけれども現在でも通用する作品です、と。
そこで「では早速読んでみます」と応じたものの、この小説は電子書籍化されておらず、amazonのユーズドで買いました。
私が手にしたのは「新版」と銘打たれた2001年刊行の文庫本ですが、この作品が最初に出版されたのは1978年です。40年近く前に書かれたものですから、いま読むと、現実に即していない設定も少なくありません。
ここで、唐突ですが、『誰がタブーをつくるのか? (河出ブックス)』(永江朗、河出書房新社=この本は2014年8月初版刊行の新刊です)の「序章」から、一部を引用します。
特定秘密保護法に関しては、日本ペンクラブをはじめたくさんの表現者団体や市民団体、有識者などから反対声明が出された。国会周辺での抗議デモもあった。そうした抗議は正当なものだが、そのなかで、この法律ができるとすぐにでも日本がかつてのアジア太平洋戦争中のような状態になるかのように主張するのはどうかと思う。国家はもっと巧妙にやるだろう。彼らも歴史に学んでいるのだ。ハードな抑圧はかえって反発を招く。それよりも、もっとソフトに、さらには国民自らが望んで規制されるような状態にコントロールしようとするだろう。少なくともぼくが権力者ならそう考える。それは決してSFの話ではない。
(永江朗『誰がタブーをつくるのか』p.25-26)
西村京太郎の『盗まれた都市』が扱っているのが、まさに、これです。
SFではありません。ミステリーです。
ミステリーゆえ、これ以上の詳しい内容はあえて書きませんが、描かれているテーマは、現在でも十分に通用するどころか、現在だからこそ、読まれるべきではないかとすら思えるものです。
事件を解決する主人公は、十津川警部ではなく、私立探偵の左文字進です。左文字進は、西村京太郎作品では『消えた巨人軍』などに登場する人物ですが、近年では水谷豊さんがテレビドラマで演じている印象のほうが強いこともあり、小説を読んでいても、カギカッコの中の文字は頭の中で水谷豊さんの声に変換されてしまうことが多く、少し、戸惑いました(笑)。
『なぜローカル経済から日本は甦るのか』冨山和彦(PHP新書932)
Posted by 大熊 一精 on 2014年10月18日(土) 19:59
『なぜローカル経済から日本は甦るのか』冨山和彦(PHP新書932)
タイトルはキャッチーですが、この本の内容をうまく言い表しているのは、むしろ、副題の「GとLの経済成長戦略」のほうです。Gとはグローバル(国際経済)、Lとはローカル(地域経済)。
どういうことか?
「G」、すなわち、グローバルについては…
国際的に取引され得る生産物は、経済のボーダレス化の中にあっては、価格(コスト)面でも、性能面でも、世界を相手にしなければならない。だから、グローバルに取引され得る商品を扱っている企業(主として製造業)は、世界チャンピオンにならない限りは淘汰されてしまう。したがって、世界チャンピオンを目指して、厳しい生存競争を勝ち抜かなければならない。
一方の「L」、すなわち、ローカルは…
国際的に移動できない生産物(サービス)は、海外と戦うことは、そもそもあり得ない。たとえば地域のバス会社が提供する公共交通というサービスを利用する人は、そのサービスに不満があるからといって、他の地域のサービスを利用するわけにはいかない。だから、「L」に属する経済セクターは、世界チャンピオンを目指す必要はない。だからといって「L」は何もしなくてよいわけではない。「L」が目指すべきは、世界チャンピオンではなく、県大会の優勝者である。
そして、日本国民(就業者)の多くは「L」に属しているにも関わらず、一般に語られる日本経済のあり方は「G」を前提にしている、それは高度成長期までは妥当であったが現在では当てはまらない。
だからといって、「G」ではなく「L」を中心に考えるべきだ、というわけではなく、「G」も応援しなければならないし「L」も大事にしなければならない、「G」と「L」は並列で論じていくべき事項である…
こうしたことが、著者自身の経験に基づく知見と、各種のデータによって、丁寧に説明されています。
内容は非常に多岐にわたっており、経済や金融に縁がない方にはやや手強いと感じられるかもしれませんが、著者が経験した具体的なエピソードやそこから得た肌感覚と、理論や統計とのバランスが非常によくとれており、また、難しい話を簡単に伝えるための喩え話がとてもうまいので、読みやすい本にまとまっています。
私がこの本をできるだけ多くの方に読んでいただきたいと思うのは、私自身の経験=1990年代に行なってきた経済や金融の調査研究、メガバンク以前の大手都市銀行内での仕事、東京から札幌への転居、ベンチャーの起業への関与、地場の中小企業とのお付き合い=の中で感じてきた多くのことが、この本に書かれている内容と合致しているからです。
それは具体的に何か?という話を書き始めると、この数倍の分量になってしまいそうなので、それはまた、いずれ、どこかで機会があれば、ということで。
『サッカーと人種差別』陣野俊史(文春新書987)
Posted by 大熊 一精 on 2014年10月18日(土) 09:37
『サッカーと人種差別』陣野俊史(文春新書987)
サッカーと人種差別、というテーマで、すぐに思い出すのは、今年の春にJリーグの試合会場のスタンドに掲げられた「JAPANESE ONLY」の横断幕です。今年4月、スペインリーグの試合で、プレー中にバナナを投げ込まれた選手(バナナを投げ込むことは黒人選手への差別を表す)が、その場でバナナを食べたことが世界的に話題になったことは、まだまだ記憶に新しい出来事です。
そうした行為について、そのときどきで論評するのは、インターネットで即時に情報が伝わる現在では、さほど難しいことではないでしょう(現に「JAPANESE ONLY」の写真は、あえてそれを探したわけでもない私でも、何度も目にしました)。そして「差別は、よくない」と断ずるのも、当たり前であり、簡単なことです。
そうした中にあって、この本の価値は、海外(おもに欧州)のサッカーの周辺で起きている人種差別について、数多くの事例を収集していることにあります。引用が多いため、著者の地の文とは違うリズムの文章が入り混じり、最近の新書(短時間ですーっと読めるものが多い)にしては若干の読みづらさはありますが、むしろ、そこが、この本のポイントです。
この本そのものから結論を得るのではなく(結論を求めれば「差別は、よくない」に決まっています)、自らの日常にフィードバックするためのヒントを得ることのできる本、読者に多くの問いかけをしている本です。
スタジアムの中が特殊なのではない。人種差別的言葉の応酬が起こる背景には、その言葉が普通に使われる社会が存在する。社会の中で人種差別的言葉が横行しているからこそ、普通にスタジアムの中でも用いられている。特にメディアにのらないようなアマチュアが大勢を占める試合では、差別語の洪水となる。有名企業が有名選手を使って行うキャンペーンの限界がここにある。メディアの領域の外で差別が野放しになっている−−-そんなメカニズムが出来ている。
(第3章「差別と闘う人びと」)
※電子書籍(Kindle)で読みました。
このたび、こちらに書評を掲載させていただくことになりました。書評というのもおこがましく、読書後のよろず雑文、という感じになるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。